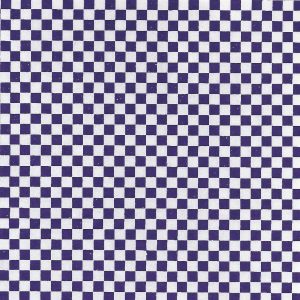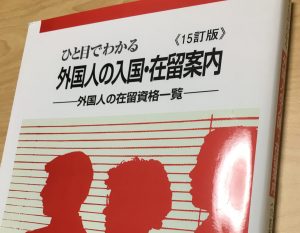今年の4月、法務省から永住許可に関するガイドラインがあらたに改定されましたが、この中でこれまで原則10年必要だった在留期間が緩和された点は大きな変更だと思います。
Contents
原則10年在留に関する特例
原則10年在留に関する特例とは、これまで永住許可の要件の一つには居住要件として『引き続き10年以上本邦に在留していること』、
つまり永住許可を得るには10年もかかることとなっていましたが、今回のガイドライン改定ではそれが大幅に見直され、幾つかある特例ケースに該当する場合、最短1年という在留期間で居住要件を満たすこととされました。

特例ケース①
日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
日本人や既に永住者となっている人と結婚している場合は、10年の在留期間がなくても結婚して3年以上経過して1年以上日本に住んでいることで居住要件を満たすということです。
例えば、海外で日本人と3年以上婚姻生活が続いている夫婦が、日本に移住した場合、僅か1年以上の在留期間で永住の申請が行えます。(他の要件OKなら)
特例ケース②
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間をして居住を認める者と定義されていますが、例えば、日系3世・日系3世の配偶者・日系2世・日系2世の配偶者であったり、定住者や日本人の配偶者の未成年で未婚の実子の方が該当します。
特例ケース③
難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
特例ケース④
外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
各分野における我が国への貢献。というのが具体的ではないのですが、こちらも当ガイドラインにて詳細に明記されています。
例えば、各分野に共通するものとしてノーベル賞やフィールズ賞を受けたことがある場合や日本政府から国民栄誉賞,文化勲章などを受けたことがある者。
外交分野では、国際機関の事務局長、事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務したことある者。
経済・産業分野では、日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営におおむね3年以上従事している(した)者。
文化・芸術分野では、文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者。
教育分野では、日本の大学などで教授,准教授又は講師として,日本でおおむね3年以上教育活動に従事している(した)者。
研究分野では、研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる者。
スポーツ分野では、オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者。
その他の分野では、社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者。
特例ケース⑤
地域再生法に基づき認定された地域再生計画において区域内に所在する公私の機関で特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら運営する者で、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること。
特例ケース⑥
「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。又は、3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
特例ケース⑦
高度専門職省令に規定するポイントが80点以上の者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
こちらについては、わずか1年の在留期間で良いとされているだけあって、要件はかなり高いものといえます。
まとめ
原則10年の在留期間が必要であるところ、7つの特例ケースのいずれかに該当すれば、5年・3年・1年といった省略した期間で居住要件が満たされることになりますが、特例というだけあってどれもハードルが高いのが特徴です。
ちなみに、特例ケース①の場合、早く永住許可を得るために海外での婚姻生活を偽装して、日本で1年過ごして永住許可を得る。といったことは審査官も想定済みなので、海外での婚姻生活が真正なものであり、永住許可が得られた後もすぐに離婚しないように疑義を生じさせないようにすることが重要です。
この場合、永住許可を取得後に離婚してしまっても、その永住許可が取り消されるといったことはありません。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
最新の投稿
 News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ
News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは?
Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは? News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)
News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)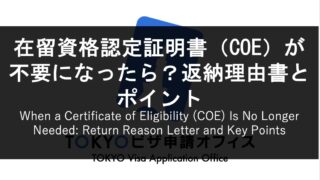 Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント
Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント