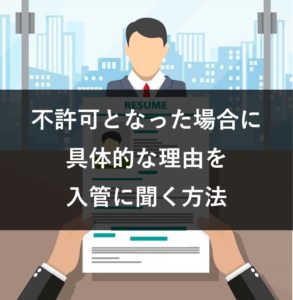在留申請手続のオンライン化がついにスタートします。
2年ぐらい前に書いたブログでは、希望的観測の内容でしたが実現まで早かった気が。
当面は、個人ベースでの申請は不可であったり、更新の申請のみだったり、申請可能な在留資格が限定されたり、予め利用申出というものを入管に行い承認を受けておく必要があったりで敷居が高い印象ですが、まずはオンライン申請が解禁されたことは非常に大きいと思います。
また、更新や変更時の在留カード受取りについても、郵送での受取りがOKになることも大きなメリットです。
Contents
在留申請オンラインシステムの主な内容
- 「在留申請オンラインシステム」を利用して実際に申請可能となるのはいつから?
- 2019年7月25日(木)から申請可能ですが、オンライン申請を利用するためには予め利用申出を行い承認を受けておく必要があります。
- 「在留申請オンラインシステム」のメリットは?
- 入管に行く必要はなく自宅やオフィス等から、オンラインで24時間申請が可能です。
また、在留カードの受領についても、一定の場合には郵送による受領が可能です。
- 「在留申請オンラインシステム」は誰が利用できる?
- ① 外国人雇用状況届出を行っているなど一定の要件を満たす外国人の所属機関(以下「所属機関」という。)の職員の方。
② 申請取次が可能な弁護士や行政書士。(①からの依頼が必要。)
- 「在留申請オンラインシステム」は法人以外の所属機関でも利用できる?
- 法人でない個人事業主等も、利用申出の承認要件を満たしている場合は利用可能です。
- 利用申出とは?
- オンライン申請を利用するために必要な申し出です。
事前に所属機関の所在地を管轄する入管に出向き、必要書類を提出し審査を経て承認を受ける必要があります。

利用申出の承認要件とは
「在留申請オンラインシステム」でオンライン申請を利用するためには、幾つかの条件があります。
その中の一つがまずはこのシステムを利用するための条件である利用申出を行い承認を得ることです。
利用申出の承認要件は以下のとおり。
- オンライン申請の受付対象となる外国人の所属機関であること。
- 過去3年間、複数回の在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請などの在留申請の手続を行っていること。
- 所属機関又はその役員が出入国又は労働に関する法律の規定により罰金以上の刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること。
- 役員が禁錮以上の刑に処せられたことがある場合、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していること。
- 過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること。
- 過去3年間、所属機関が在留資格を取り消された外国人の当該取消しの原因となった事実に関与したことがないこと。
- 所属機関が外国人の受入れの開始、終了等の届出を行っていること。(注1)
なお、外国人労働者の雇入れ、離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークに届け出ることを義務付けられている事業主は、その届出を行っていること。(注2)
(注1)入管法第19条の17に基づく所属機関による届出
(注2)労働施策総合推進法第28条第1項に基づく外国人雇用状況の届出 - 利用申出の受付の際に提出させる誓約書(別記第2号様式)による誓約を行っていること。
- 利用申出の不承認歴がある場合には、不承認となった理由が払拭されていること。
利用申出に必要な提出書類とは
必要書類は所属機関の種類によって異なりますが、基本となるのは以下のとおり。
- 在留申請オンラインシステム利用申出書
- 利用申出の承認を受けようとする方の在職証明書(発行後3か月以内のもの。)
- オンラインでの手続の代行に係る依頼及び新規利用申出に係る依頼を受けていることが分かる資料
(届出済弁護士や行政書士が利用申出を行う場合。) - 誓約書
- 所属している外国人リスト
- 所属機関のカテゴリーを立証する資料
- 利用申出を行ってから結果が出るまでの期間は?
- 1週間から2週間程度ですが、最初は当システムの運用開始となる7月25日から順次結果の通知が行われます。
- 新規・追加の利用申出に手数料は必要?
- 利用申出にも承認を受けた場合にも手数料はかかりません。
オンライン申請で行える申請の種類は
個人的に気になってたところですが、当面は更新申請がメインとなっています。
①在留期間更新許可申請
②再入国許可申請
③資格外活動許可申請
※②及び③の申請は①と同時申請の場合に限定。
また、更新の申請なら全てオンライン申請が利用できるわけではなく、在留資格ごとに対象範囲が異なります。
例えば、「経営・管理」の在留資格の方が、オンライン申請で更新をしようとする場合、所属機関がカテゴリー1か2でなければなりません。
同様に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方の場合も、所属機関がカテゴリー1か2でなければオンライン申請は利用できません。
この辺りがまだ敷居が高いといえますが、最初は仕方ないでしょう。

- 再入国許可申請や資格外活動許可申請のみを個別に「在留申請オンラインシステム」で申請できますか?
- 再入国許可申請と資格外活動許可申請は更新申請と同時に行う場合に限り、オンライン申請での受付が可能です。
それ以外の場合は、入管に直接行って申請を行う必要があります。
- 在留期間満了日の当日に「在留申請オンラインシステム」で申請できますか?
- できません。
期間満了日の当日はオンライン申請での受付ができませんので、満了日に入管に直接行って申請を行う必要があります。
- 在留期限を過ぎてしまいました。この場合「在留申請オンラインシステム」で申請できますか?
- できません。
在留期限を経過した場合、オンライン申請での受付はできません。
速やかに最寄りの入管に直接行って、必要な手続について相談する必要があります。
在留カードの受取りについて
- 「在留申請オンラインシステム」で申請した場合、在留カードはどのように受取りできますか?
- オンライン申請の内容入力時に、在留カードは、郵送による受取り or 入管窓口で受取りのいずれかを選択できます。
ただし、次のケースでは郵送による受取りはできません。
・更新許可申請と同時に再入国許可申請や資格外活動許可申請を行っている場合
(旅券への証印による再入国許可や資格外活動許可が必要であるため)
・在留カードの交付ではなく、旅券への証印により許可を行う場合
(例:「公用」の在留資格、3月以下の在留期間が決定された方)
・在留カードに漢字氏名併記の申出を行う場合
(氏名に漢字を使用する中長期在留者で所持する在留カードにローマ字による氏名のみが表記されている場合が該当します)
※既に漢字併記されてる方は郵送可能
・在留カードの有効期間更新申請を伴う場合
(例:新しい在留カードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるとき)
- 「在留申請オンラインシステム」で申請した場合、窓口での受取りはどうすればいいですか?
- オンライン申請を利用して、在留カードを郵送受取ではなく直接入管の窓口で受取ることを希望する場合は、メールの案内に従い以下4点を用意して直接入管の窓口に行ってください。
・当申請人のパスポート
・在留カード
・所定の収入印紙を貼った手数料納付書
・「審査完了に関するお知らせ」メールの写し (スマホ等にて提示でもOK)
- 在留カードを郵送での受領手続中のため、手元に在留カードがありません。警察官から提示を求められた場合はどうすれば良いですか?
- 在留カードを郵送前に両面のカラーコピーを作成し、裏面に最低でも以下の事項を記載の上、新しい在留カードを受取るまでの間は、この在留カードの写しを必ず携帯してください。
郵送の場合等、手元にパスポートが残る場合、併せてパスポートも所持してください。
表面記載の外国人は,現在オンラインで○○申請中である。
オンラインシステム利用者(取次者)氏名:○○ ○○(職業:○○)
オンラインシステム利用者(取次者)の連絡先:○○○-○○○○-○○○○
申請受付日:○○○○年○○月○○日
申請受付番号:○オンE○○○○○○○
- 在留カードを郵送での受領手続中のため、手元に在留カードがありません。みなし再入国許可による出国は可能ですか。
- 在留カードが交付されている外国人の方が”みなし再入国許可”による出国するためには、有効な在留カードを所持することが法律上定められています。
在留カードを所持していない場合は”みなし再入国許可”による出国はできません。
- 在留カードの送付先を申請人本人の住居地等,希望する場所に変更できますか。
- 希望する場所への変更はできません。
在留カードを郵送で受取る場合、送付先は次のとおりです。それ以外の送付先に変更することはできません。
<利用者が所属機関の職員の方である場合>
利用申出書に記載された所属機関の所在地
<利用者が届出済弁護士・行政書士の方である場合>
利用申出書に記載された届出済弁護士・行政書士の方の所属事務所の所在地
参考法令
入管法
(所属機関による届出)
第十九条の十七 別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
出典:e-Gov法令検索
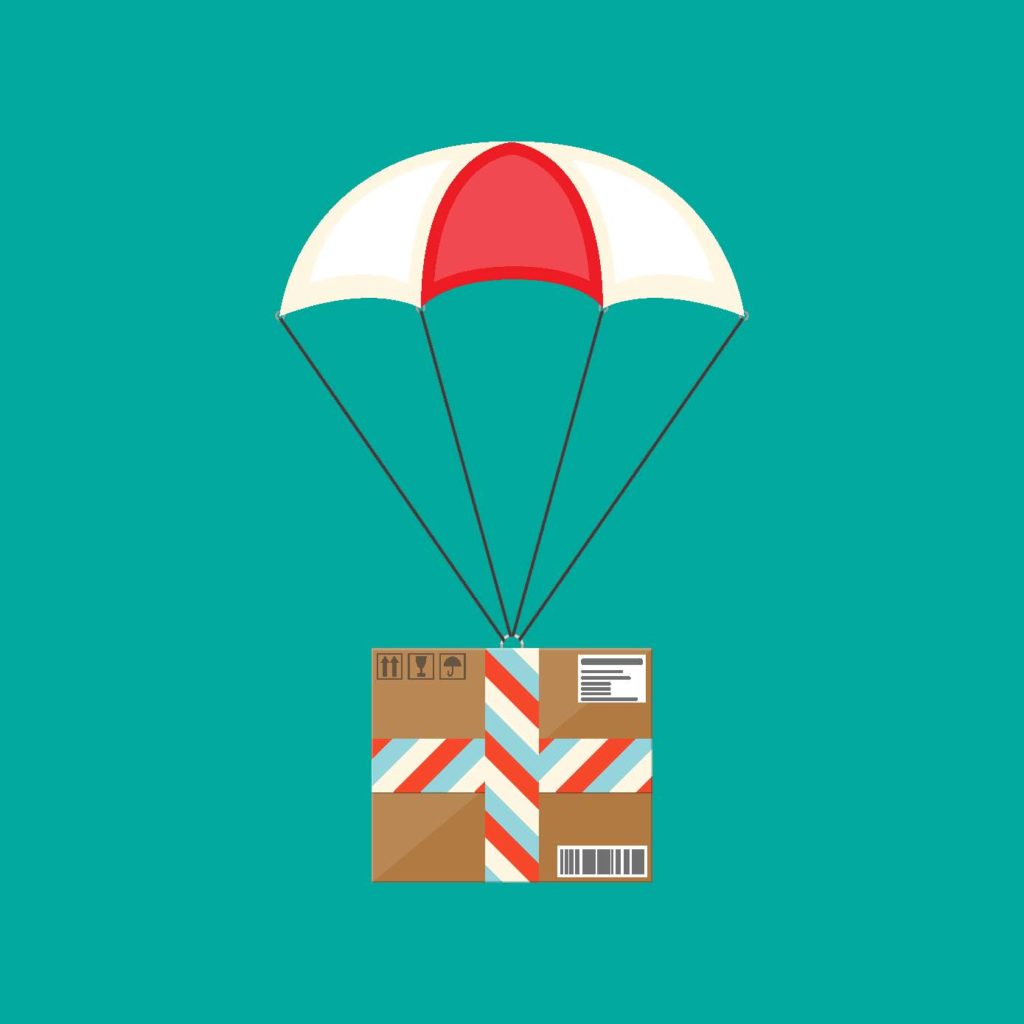
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
最新の投稿
 News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ
News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは?
Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは? News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)
News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)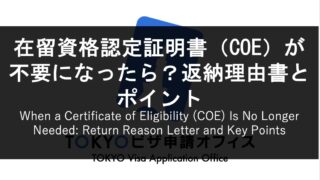 Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント
Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント