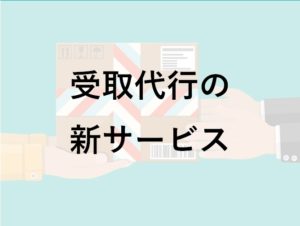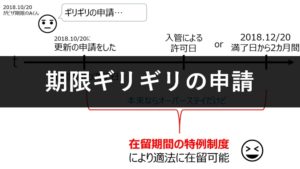特定技能の外国人を雇うための、受入れる機関(会社など)にはいくつかの基準が定められています。
今回はそんな受入れ機関の基準についての解説。
※受入れ機関の基準は、今回の入管法改正で新たに整備された特定技能基準省令にて細かく定められており、受入れ機関の基準は主に第2条に記されています。
Contents
特定技能を受入れる機関の基準とは
まずは法が定めている受入れ機関の基準を確認。
主に1~12号にて構成されています。
※ 以下‟雇用契約”と記載のあるものは‟特定技能雇用契約”を意味します。
※ 特定技能基準省令第2条の内容ですが、一部読み易くするために加工しています。
- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
- 受入れ機関が過去1年間、当雇用契約において労働者を離職させていないこと
- 受入れ機関が過去1年間、外国人の行方不明者を発生させていないこと
- 受入れ機関が適正であること
- 雇用契約に関する外国人の‟活動内容に係る文書”を作成すること
- 外国人がブローカー等により保証金の徴収、違約金契約、その他不当な財産の契約を締結させられている場合は、当雇用契約を締結しないこと
- 特定技能の外国人の支援に要する費用について、当外国人に負担させないこと
- 特定技能の外国人を派遣しようとする受入れ機関は、次のいずれにも該当すること
- 事業に関する労働者災害補償保険の届出、その他これに類する措置があること
- 雇用契約を継続、履行する体制が適切に整備されていること
- 給料は振込み、又は確認可能な方法によって支払うこと
- 特定産業分野毎の告示で定める基準に適合すること
なかなかボリュームありますが、それぞれ補足していきます。
そして全て見てもらうと‟案外当たり前のことだな”と感じるかもしれません。

1.労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
受入れ機関が労働関係、社会保険関係、租税関係の法令について遵守していることが求められます。
労働関係の遵守とは
労働関係を遵守しているとは、具体的には次の場合をいいます。
・労働基準法の基準にのっとって雇用契約が締結されていること
・雇用保険及び労災保険の適用事業所である場合は、当該保険の適用手続や保険料の納付を適切に行っていること。
※なお、保険料の未納があった場合でも、入管の助言・指導に基づき納付手続を行った場合には、労働関係法令を遵守しているものと評価されます。
社会保険関係の遵守とは
社会保険関係を遵守しているとは、具体的には次の場合をいいます。
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合>
・受入れ機関が、健康保険・厚生年金保険の加入手続、従業員の被保険者資格取得手続を行っており、所定の保険料を納付していること。
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合>
・受入れ機関(事業主本人)が、国民健康保険・国民年金に加入し、所定の保険料を適切に納付していること。
なお、社会保険料の未納があった場合でも,入管の助言・指導に基づき保険料を納付した場合には、社会保険関係法令を遵守しているものと評価されます。
租税関係の遵守とは
租税関係を遵守しているとは、具体的には以下の場合をいいます。
<法人の場合>
受入れ機関が、国税・地方税を適切に納付していること。
<個人事業主の場合>
受入れ機関が、国税・地方税を適切に納付していること。
※ 国税 → 源泉所得税、復興特別所得税、法人税、消費税、地方消費税のこと
※ 地方税 → 法人住民税のこと
納付すべき税に未納があった場合でも、入管の助言・指導に基づき納付した場合には,租税関係法令を遵守しているものと評価されます。
ただし、特定技能の外国人から特別徴収をした住民税を、受入れ機関が納入せずに未納があることが判明した場合には,租税法令を遵守していないものと評価されます。
2.受入れ機関が過去1年間、当雇用契約において労働者を離職させていないこと
受入れ機関が、現に雇用している国内労働者を非自発的に離職させ、その補填として特定技能外国人を受け入れることは、人手不足に対応するための人材の確保という本制度の趣旨に沿わないことから、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないことを求めるものです。
雇用契約の締結の日の1年前のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を発生させていないことが求められます。
ただし、以下のケースの離職者は問題ありません。
・定年その他これに準ずる理由により退職した者
・自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者
・期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の期間満了時に当該有期労働契約を終了された者
・自発的に離職した者
3.受入れ機関が過去1年間、外国人の行方不明者を発生させていないこと
受入れ機関が雇用する外国人について責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている場合には、当該機関の受入れ体制が十分であるとはいえないことから、雇用契約締結の日の前1年以内及び当該契約締結後に行方不明者を発生させていないことを求めるものです。
特定技能雇用契約の締結の日の1年前のみならず、特定技能雇用契約を締結した後も外国人の行方不明者を発生させていないことが求められます。
※「責めに帰すべき事由」とは、受入れ機関が、雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合や、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合など、法令違反や基準に適合しない行為が行われていた期間内に、特定技能外国人が行方不明となった場合を指します。
4.受入れ機関が適正であること
“適正であること”というのは、曖昧ですが、中身は次のように細かく規定されています。
次のいずれかに該当する者が、関係法律による刑罰を受けている場合には、欠格事由に該当し、受入れ機関になることはできません。
・禁錮以上の刑に処せられた者
・出入国又は労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
・暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
・社会保険各法及び労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者
いずれも、「刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」がその対象となります。
また、精神の機能の障害により雇用契約の履行を適正に行うことができない者や、破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者なども受入れ機関になることはできません。
また、過去5年の間に技能実習の実習認定を取り消された者、外国人に対して暴行、脅迫、監禁行為、旅券又は在留カードを取り上げる行為、報酬の一部又は全部を支払わない行為、外出その他私生活の自由を不当に制限する行為などを行った者も受入れ機関になることはできません。
他にも、保証金の徴収、財産の管理、当該雇用契約の不履行に係る違約金を定める契約、不当な財産の移転を予定する契約を締結する行為も禁止されています。
5.雇用契約に関する外国人の‟活動内容に係る文書”を作成すること
受入れ機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成しなければなりません。
また、その雇用契約が終了した後も事業所には1年以上備えておく必要があります。
‟活動の内容に係る文書”には、大きく2つあります。
- 特定技能外国人の名簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・氏名
・国籍
・地域
・生年月日
・性別
・在留資格、在留期間、在留期間の満了日
・在留カード番号
・外国人雇用状況届出の届出日
など - 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿(必要的な記載事項は以下のとおり)
・就労場所
・労働保険の適用状況
・社会保険の加入状況
・安全衛生の確保状況
・従事した業務の内容
・雇用内容、雇用状況、雇用契約に関する内容
・出勤状況に関する書類
・支援に要した費用の額及び内訳
・休暇の取得状況
など
6.外国人がブローカー等により保証金の徴収、違約金契約、その他不当な財産の契約を締結させられている場合は、当雇用契約を締結しないこと
受入れ機関は、特定技能の外国人と雇用契約を締結するに当たり、当外国人又はその配偶者、その他親類等が第三者(ブローカー等)との間で保証金の徴収・不当な財産の移転を予定する契約・違約金契約を締結させられているなどの場合には、そのことを認識して特定技能雇用契約を締結していないことを求めるものです。
※ ここで言う‟第三者”には、日本国内外の仲介事業者、登録支援機関、職業紹介事業者、更に受入れ機関自身も含め、幅広く規制の対象となっています。
※ ‟不当な財産の移転を予定する契約”とは、
・受入れ機関から失踪した場合に雇用契約の不履行があったものとしていて違約金を定める契約
・休日の外出を許可制にして許可を得ずに外出したとして違約金を定める契約
・作業時間中にトイレ等で離席すること等を禁じて、その違約金を定める契約
・商品若しくはサービスの対価として不当に高額な料金の徴収を予定する契約
などが該当します。

7.特定技能の外国人の支援に要する費用について、当外国人に負担させないこと
特定技能の外国人に対しては様々な支援を行うことが義務付けられていますが、その支援に要する費用は、受入れ機関等において負担すべきものとされています。
なお、直接的は勿論、間接的にも負担させてはならないものとなっています。
今回の特定技能の制度では、技能実習制度の反省点を活かして外国人を保護することが趣旨としてあるからです。
8.特定技能の外国人を派遣しようとする受入れ機関は、次のいずれにも該当すること
- 派遣先にて従事する業務も特定産業分野、又はこれに関連する業務を行っている者であること。
※ 派遣が認められるのは当面は農業分野と漁業分野のみ。 - 派遣先についても、派遣元である受入れ機関と同様に、労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。
- 同じく派遣先についても、4号の欠格事由に該当しないこと。
9.事業に関する労働者災害補償保険の届出、その他これに類する措置があること
特定技能外国人への労働者災害補償保険の適用を確保するため、受入れ機関が労災保険の適用事業所である場合には、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していることを求めているものです。
‟その他これに類する措置”とは、受入れ機関が労災保険制度において暫定任意適用事業とされている農林水産の事業の一部を想定したものです。
この場合は、労災保険に類する措置あるものとされます。
10.雇用契約を継続、履行する体制が適切に整備されていること
雇用契約を継続して履行する体制として、受入れ機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していることをいいます。
確認書類として以下のものが必要となります。
<法人の場合>
・決算文書(貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書)の写し(直近2年分)
・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
<個人事業主の場合>
・税目を申告所得税の納税証明書(その2)(直近2年分)
11.給料は振込み、又は確認可能な方法によって支払うこと
特定技能外国人に対する給料の支払は確実で適正なものにする必要があるため、当該外国人に対し、給料支払方法として預金口座への振込みがあることを説明した上で、同意がある場合には、預貯金口座への振込みにより行うことが求められます。
振込み以外の支払方法も可能とされていますが、その場合には、後に入管から支払の事実を証する客観的な証拠資料の提出が求められることがあります。
12.特定産業分野毎の告示で定める基準に適合すること
特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて、個別に定める基準に適合していることを求めるものです。
ここで言う‟特有の事情”とは、特定産業分野毎に定められている受入れ可能人数枠のことです。
1件から御対応承っております。ご連絡心よりお待ちしております。03-4361-4503受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝以外 ]
お気軽にお問い合わせください Please free to contact us.ビザ関連情報をお届けします。
よかったらいいね /フォロー をお願いします。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
最新の投稿
 News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ
News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは?
Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは? News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)
News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)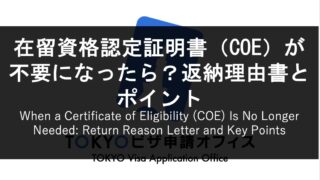 Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント
Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント