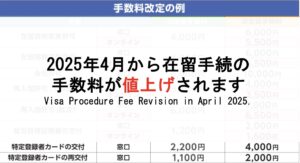2019年に新設された「特定活動(告示46号)」(本邦大学等卒業者)は、外国人留学生の就職範囲を大きく広げる在留資格です。このビザにより、日本の大学などを卒業した高度な日本語力を持つ外国人が、これまでの就労ビザでは認められなかった業務にも就けるようになりました。
本記事では、その特定活動46号ビザの目的や認められる活動内容、取得要件、申請手続き、メリット・注意点などをガイドラインに基づきわかりやすく解説します。外国人材を採用したい企業担当者や日本で働きたい留学生・元留学生の方、ビザコンサルタントの方々の参考になれば幸いです。
Contents
特定活動46号ビザの概要と背景
特定活動46号ビザ(本邦大学等卒業者)は、日本の大学・大学院等を卒業した留学生で高い日本語能力を持つ人材に対し、これまで就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)では認められなかった幅広い職種での就労を可能にした在留資格です。少子高齢化による人手不足が深刻化する中、現場業務を含む幅広い業務への外国人材の参画を促す目的で2019年5月に創設されました。例えばサービス業や製造業など、「技人国」の制約下では従事できなかった現場作業を伴う職種にも、特定活動46号なら従事可能となります。
この在留資格では、申請人ごとに法務大臣が活動内容を指定する「指定書」が発行されます。活動の範囲は告示によって定められており、その46番目にあたる類型であることから「告示46号」と呼ばれます。一方、告示にない個別対応の特定活動(告示外特定活動)も多数存在しますが、特定活動46号は告示に明記された類型の一つです。
背景として、2019年の入管法改正では「特定技能」の創設が注目されましたが、同時期に外国人留学生の就職先拡大に関するこの新しい特定活動も導入されています。従来、留学生が日本で就職する場合、多くは「技人国」ビザへの変更を行ってきました。しかし「技人国」はあくまでホワイトカラー職(頭脳労働)向けのビザであり、職務内容が大学等で専攻した専門知識に関連している必要があります。現実の職場では、デスクワークと現場作業が混在するケースも多く、中小企業ほど一人の社員が様々な業務を兼務する傾向があります。そのため、留学生がせっかく日本企業に就職しても、「技人国」の要件に外れる現場業務に携われないという壁がありました。産業界からの「もっと幅広い職種で留学生を雇用できるようにしてほしい」という要請を受け、要件を緩和した在留資格として創設されたのが特定活動46号です。
特定活動46号で認められる活動内容
特定活動46号ビザでは、一般的なサービス業務や製造業務など幅広い業務への従事が認められます。これは、日本の大学等で習得した知識や応用能力、留学生としての経験を通じて得た高い日本語力を活用することを要件としているためです。
具体的には、ホテル勤務を例にとれば、フロント業務(これは通常「技人国」で認められる事務職的業務)に加え、コンシェルジュやドアマンとして荷物運び・案内など現場サービスにも従事できるようになります。製造業でも、研究開発業務とライン作業の両方を行うといったケースで、後者の現場作業部分も含めて担当することが可能になります。このように頭脳労働と現場作業が混在した職務をカバーできる点が特定活動46号の大きな特徴です。
ただし、あらゆる業務が無制限に許可されるわけではありません。以下のような制限事項があります。
- 法律上の資格が必要な独占業務には就けない。医師や弁護士など、国家資格を有する者しか従事できない業務については、このビザであっても当然ながら資格が無ければ行えません。そうした専門職に就く場合は、それ専用の在留資格(「医療」や「法律・会計業務」等)の取得が必要です。
- 風俗営業に関わる業務には就けない。ナイトクラブやバーの接待業務など、風俗営業法に基づく業務への従事は禁止されています。これは他の就労ビザと同様の制限で、特定活動46号だから特別に許可されるということはありません。
また、実際に従事する業務では日本語力や専門知識を活かすことが求められます。ガイドラインでは「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含むこと、と説明されています。言い換えれば、単に指示を聞いて動くだけの作業ではなく、日本語で円滑にコミュニケーションしながら遂行する業務である必要があります。例えば単純労働的な作業でも、日本人スタッフや顧客との十分な対話・意思疎通が求められる環境であれば問題ありませんが、日本語をほとんど使わずに済んでしまうような業務内容だとビザの趣旨に合致しない可能性があります。この点については後述する日本語能力要件とも関係します。
以上のように、特定活動46号は「幅広い業務が可能になるが、日本で学んだ知識や日本語力を活かすこと」という条件付きの就労ビザと捉えるとよいでしょう。許可される業務範囲は広い一方で、日本で高等教育を受け高い語学力を身につけた人材だからこそ従事できる仕事であることが求められているのです。
特定活動46号の取得要件(対象者)
特定活動46号ビザを申請できるのは、「本邦大学等卒業者」であってなおかつ「高い日本語能力」を有する方と定義されています。ガイドラインに沿って、具体的な要件を学歴・日本語能力・その他条件に分けて説明します。
要件1:本邦大学等卒業者であること(学歴要件)
「本邦大学等卒業者」とは、日本国内の高等教育機関を修了した者を指します。該当する学歴の範囲は次の通りです。
- 日本の大学(学部)を卒業し学士の学位を取得した者(※短期大学を除く)
- 日本の大学院を修了し修士または博士の学位を取得した者
- 日本の短期大学または高等専門学校を卒業した者で、さらに専攻科を修了して学士の学位を取得した者
- 日本の専修学校専門課程(いわゆる専門学校)を修了した者で、文部科学大臣が認定する「職業実践専門課程」等の指定を受けたコースを修了し高度専門士の称号を取得した者
上記に該当する人が「本邦大学等卒業者」です。簡単にまとめると、日本の4年制大学卒業者や大学院修了者はもちろん対象になります。また短大・高専卒の場合は追加の専攻科経由で学士取得が必要、専門学校卒の場合は文科省認定の高度専門士コース修了者のみ対象となります。単に短大を出ただけ、通常の専門学校コースを出ただけでは特定活動46号の対象にはならない点に注意が必要です。
一方で、外国の大学を卒業しただけの方や外国の大学院を修了した方、あるいは認定を受けていない専修学校専門課程の修了者は対象外となります。この在留資格はあくまで「日本国内の教育機関を卒業した留学生」の就職支援を目的としているため、海外大学卒業者など「本邦大学等卒業者」に当てはまらない学歴の方は申請資格がありません。
要件2:高い日本語能力を有すること(日本語能力)
申請者には高度な日本語コミュニケーション能力が求められます。ガイドラインでは具体的な基準として日本語能力試験(JLPT)N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有することが挙げられています。旧日本語能力試験でいう「1級」相当も含まれます。この条件を満たすことで「高い日本語能力」を有する者と認められます。
なお、例外的な計らいとして大学や大学院で日本語を専攻して卒業した外国人については、日本語能力試験等の結果がなくても同等の日本語力があるとみなす運用も示されています。ただしその場合であっても前述の学歴要件(日本の大学等卒業者であること)は別途満たす必要があります。つまり「外国の大学で日本語専攻卒業した」だけでは対象にならないので注意してください。
求められる日本語力は単に試験合格という形式的なものではなく、実践的なコミュニケーション力です。ガイドライン上も「日本語で円滑に双方向の意思疎通を行える能力」が必要とされています。そのため「指示を聞いて理解する程度の受動的な日本語力では不十分」とされ、職場で日本人と対等にやり取りできるレベルが求められると考えてください。
その他の要件・留意事項
上記学歴と日本語という2つが特定活動46号の主要要件ですが、他にも一般的な就労ビザと同様の条件があります。
- 雇用契約条件(給与要件):日本人が従事する場合と同等額以上の給与報酬を受けること。これは全ての就労系在留資格に共通する要件で、日本人社員と比べて極端に低い給与で雇用することは認められません。賞与や各種手当なども含め、同種業務に従事する日本人と同水準かどうか入管で審査されます。
- 勤務先となる企業の安定性:申請時には受入れ企業(雇用先)の概要資料や決算書類等を提出します。他の就労ビザ同様、企業の規模や事業の安定性も審査の対象です。新設間もない企業や零細企業の場合、追加資料の提出など厳密にチェックされる傾向があります。これは入管側が「雇用先がすぐ倒産したり給与未払いになったら本人が不安定になり、不法残留につながりかねない」と懸念するためです。
- 現在の在留資格:申請時点で日本に在留している場合、通常は「留学」からの資格変更で申請します。しかし既に他の就労資格で働いている元留学生や一度卒業後帰国した元留学生でも、学歴・日本語要件を満たせばこの資格を新規取得することが可能です。その場合は在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請(COE申請)によって特定活動46号を取得する形になります。
- 素行要件:これも他のビザと同様ですが、過去に在留資格違反や重大な法令違反がないことが前提となります。例えば留学中に資格外活動の制限(週28時間など)を大幅に超えて違法就労していたような場合、たとえ学歴や日本語の条件を満たしていても不許可となった事例があります。日頃から遵法意識を持って生活していることが大切です。
以上が主な取得要件です。
まとめると、「日本の大学等を出ていること」「N1レベルの日本語力があること」「日本人と同等の処遇で安定企業に雇用されること」が満たされれば、特定活動46号の枠組みで幅広い就職が可能になるということです。逆に言えば、日本での学歴や日本語力が十分でない場合はこのビザの対象にならないため、その場合は通常の「技人国」ビザや別の在留資格での就労を検討する必要があります。
申請手続きと必要書類
特定活動46号ビザの申請手続きは、大きく分けて「在留資格変更許可申請」(日本にいる留学生が卒業後に留学ビザから切り替える場合)と「在留資格認定証明書交付申請」(一度帰国した元留学生などが海外から新規に呼び寄せる場合)があります。いずれも受入れ企業等が決まり、雇用契約を締結した上で申請を行います。
変更の場合(留学ビザからの変更)
日本で在学中または卒業後に引き続き在留している場合、在留資格「留学」から「特定活動(本邦大学卒業者)」への変更申請を行います。申請先は現在居住している地域を管轄する入管です。提出書類は他の就労ビザ申請と類似していますが、本資格固有の書類もあります。主な必要書類は次の通りです。
- 在留資格変更許可申請書:所定の様式に必要事項を記入した申請書。本資格の場合、「活動の詳細」欄に職務内容の説明や就労予定期間などを記載します。
- 卒業証明書または学位記の写し:日本の大学・大学院・短大・高専・専修学校等の卒業を証明する書類。加えて短大・高専卒で学士取得の場合は学位授与機構の学位記、専門学校高度専門士の場合は称号付与証明書なども提出します。
- 日本語能力を証明する書類:JLPT N1の合格証明書やBJTスコア証明書など。大学等で日本語専攻の場合はその証明(成績証明書や専攻証明)も添付するとよいでしょう。
- 雇用契約書(または内定通知書):受入企業との間で結んだ雇用契約書のコピー。職務内容(担当業務の具体的説明)や給与・勤務時間など労働条件が明記されたものが必要です。
- 会社の概要資料:受入企業の登記簿謄本、会社パンフレット、直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)等。これは企業の実態や安定性を示すための資料です。新しい会社の場合は事業計画書等を求められるケースもあります。
- その他:写真(縦4cm×横3cm)、パスポート・在留カードの写し、身元保証書(不要な場合もあり)など、一般的な申請と同様の書類。
入管はこれら提出資料をもとに、「学歴要件・日本語要件を満たしているか」「職務内容がガイドラインの範囲内か(現場作業ばかりではないか?日本語力を活かす内容か?)」「給与や会社の条件が適正か」を総合的に審査します。特定活動46号ガイドライン上、留学からの変更申請時および初回更新時の在留期間は原則1年とされており、最初は1年が交付されるケースが多いです(後述)。
海外から新規入国する場合(在留資格認定証明書交付申請)
一度卒業後に帰国してしまった元留学生などを、日本の企業が新たに採用する場合は在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行います。基本的な必要書類は変更申請と共通ですが、追加で本国での経歴証明などを用意することがあります。申請は受入れ企業側が代理で行い、法務省から在留資格認定証明書(交付許可)が出たらそれを海外の本人に送り、本人が日本大使館・領事館でビザ発給を受けて入国する流れです。
COE申請の場合も審査ポイントや提出資料はほぼ同様で、「学歴(日本の学校卒)」「日本語力(N1等)」「雇用条件(給与・仕事内容)」「会社の安定性」がチェックされます。特に卒業後一定期間経っているケースでは、その間の職歴や日本語力維持状況についても質問されることがあります。例えば「卒業後一旦帰国して数年間就労していた」ならその職歴証明を提出する、「日本語力にブランクがあるのでは?」と思われないよう、日本語で業務していた証拠や日本語試験の追加受験結果などを示すと良いでしょう。
家族の帯同について
特定活動46号で在留する場合、配偶者や子どもも「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で、日常的な活動が認められます。申請する場合は、上記申請と同時または後日改めて、家族について在留資格認定証明書を申請します。必要書類は他の就労ビザ保持者の家族帯同と同様で、続柄を証明する婚姻証明書や出生証明書、そして本人の収入証明(年間所得見込み額など)を提出します。十分な収入があり生活維持できることが条件となりますが、特定活動46号だから特別厳しいということはなく、要件を満たせば問題なく配偶者・子女の在留も認められます。
在留期間と更新・転職のポイント
在留期間の長さと更新制限
特定活動46号の在留期間は他の多くの就労資格と同じく、個々の審査結果によって5年、3年、1年、6か月、3か月のいずれかが付与されます。もっとも新規で許可される際には、多くの場合「1年」が選択されています。ガイドラインにも「原則として変更許可時および初回更新時は1年」と明記されており、これは特定活動46号のひとつの特徴です。例えば同じ人が「技人国」ビザを申請する場合、日本の大学卒かつ高い日本語力があれば比較的「3年」や「5年」が最初から付与される傾向があります。
一方、本資格ではどんなに優秀でもまずは1年様子見となるケースが多く、「毎年更新手続きが必要で手間」という声もあります。ただし2回目以降の更新では、勤務実績や会社での評価、企業の安定性などが認められれば3年や5年への延長も十分可能です。
更新回数に制限はありません。特定技能1号のような通算滞在期間の上限(5年まで等)は設けられていないため、条件を満たし続ける限り何度でも更新が許可されます。したがって長期的に日本で働き続けることも可能であり、一定の在留期間が経過し要件を満たせば永住許可申請を行うこともできます。実際、永住権(永住者資格)の申請要件は「原則10年在留」ですが、特定活動46号での在留期間も通算できますので、将来的には本資格のまま永住権を取得する道も開かれています。
転職や在留資格変更の注意点
特定活動46号ビザで注意すべきなのは、転職の際の手続きです。他の一般的な就労ビザ(例えば技人国)では、在留資格の範囲内であれば転職しても資格を維持できます(入管への届出は必要)。しかし特定活動46号は個別の企業・職務に対して発給されるビザであり、転職する場合は改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。ビザ発給時に交付される「指定書」には所属先(企業)や認められる活動範囲が明記されており、別の企業へ移る際には新たな指定書をもらわなければなりません。これは実質的に転職のたびにビザを取り直す手続きが必要になることを意味します。
転職先でも特定活動46号の要件(学歴・日本語・業務内容・給与等)を満たしていれば、再申請により新たな特定活動46号ビザを取得すること自体は可能です。ですが申請~許可まで時間がかかるため、在職中に次の会社の内定を得て早めに申請するなど切り替えの計画を綿密に立てる必要があります。
もし転職先の業務内容が「技人国」でカバーできる類い(純粋なホワイトカラー職)であれば、特定活動から技人国への変更という選択もあり得ます。その方がビザ上は柔軟に転職しやすくなるメリットがあるためです。このように、一度特定活動46号を取得した後のキャリアについても、転職時には在留資格をどうするかを検討しましょう。
なお、現在の勤務先で同じ業務を続ける限りにおいては更新申請だけで問題ありません。一つの会社で長期勤務する予定であれば、特定活動46号で入国・就労し、そのまま更新を繰り返していけば特に不利益なく働き続けられます。更新回数の制限も無いため長期雇用にも対応しています。
特定活動46号ビザのメリット・デメリット
最後に、この在留資格を活用するメリットと留意すべき点(デメリット)を整理します。
特定活動46号のメリット
- 外国人留学生の就職先が大幅に拡大:サービス業や製造業など、これまで留学生には門戸が狭かった業界でも優秀な人材を採用できるようになります。企業にとっては人手不足解消や多様な人材確保に繋がり、留学生にとっては希望の職種に就けるチャンスが広がります。
- 混在業務ポジションの採用が可能:フロント業務+接客、研究+生産作業などホワイトカラーとブルーカラーのミックス職種に対応できます。特に中小企業では重宝するでしょう。今までは業務内容を日本人と比べ細かく分けて制限する必要がありましたが、その煩わしさが軽減されます。
- 高度な日本語力を持つ人材の活用:日本の大学で学び日本社会に慣れた留学生は、語学・文化両面で戦力になり得ます。本資格はそうした人材の日本語力を最大限発揮できる場を提供します。社内外のコミュニケーションや海外展開の橋渡し役など、さまざまな場面で力を発揮してくれるでしょう。
- 在留期間の上限なし・長期定着可能:前述の通り更新に回数制限がなく通算上限もありません。そのため、企業としては戦力となった人材を長期雇用し幹部候補に育成するといったプランも立てやすくなります。一定年数後には永住権取得の道も開けるため、本人にとっても将来設計を描きやすいという利点があります。
- 他の在留資格との組み合わせで柔軟性:特定活動46号として働き始めても、後に仕事内容が専門的になれば「技人国」へ変更することもできますし、逆に起業を志せば「経営・管理」ビザ、専門分野を極めれば「高度専門職」ビザなど、キャリアに応じた在留資格への移行も可能です。一度この資格を取得したからといって将来の選択が狭まるわけではありません。
特定活動46号の留意点・デメリット
- 申請要件が限定的:メリットの裏返しですが、誰もが申請できる資格ではない点に注意です。日本での学位取得とN1レベルの日本語力というハードルがあるため、それを満たさない人材(例:日本の大学は出ていない・日本語がそこまで得意でない等)は対象外となります。企業としても、採用したい候補者がこの要件をクリアしているか事前に確認する必要があります。
- 初期の在留期間が短い:前述のように最初は1年ビザになるケースが多いため、企業・本人双方にとって更新手続きの手間があります。特に採用後1年で再度更新申請・審査がある点は、人事担当者もフォローが必要です。ただし順調にいけば次回以降は3年など長めがもらえる可能性があります。
- 転職の自由度が低い:転職するごとに在留資格の再申請が必要になるため、本人にとってはハードルです。新たな職場が決まってもビザ変更が不許可では困るので、どうしても消極的にならざるを得ません。企業側も途中離職を防ぐための受入れ姿勢(キャリアパス提示や待遇向上など)が重要になるでしょう。一方で、転職できないわけではなく手続きを踏めば可能なので、必要なら専門家のサポートを受けて進めることをおすすめします。
- 職務内容のミスマッチに注意:制度上幅広い業務が可能とはいえ、「何でもOK」ではありません。例えば専攻とかけ離れた職種に就かせようとすると不許可のリスクがあります。実際に「専門学校で服飾デザインを学んだ卒業生が旅館のフロント業務で申請したが、専攻と業務の関連性が認められず不許可になった例」なども報告されています。大学卒業生の場合は比較的柔軟に見てもらえますが、それでも極端に畑違いな職務だと懸念材料となるでしょう。採用ポジションと本人の経歴・スキルの関連性にも配慮が必要です。
- 申請書類準備が煩雑:これは他のビザでも似ていますが、特にこの資格は学歴証明・語学証明・業務説明など揃える書類が多岐にわたります。高度専門士かどうかの判定や、日本語専攻の証明など、場合によっては追加資料も必要です。入管のガイドラインや必要書類リストをよく読み、ミスなく準備することが大切です。専門的な内容ゆえに不安な場合は、行政書士など専門家に依頼するのも一つの方法です。
以上のメリット・デメリットを踏まえ、特定活動46号ビザは「日本で学んだ留学生を日本で活かす」ための制度だと言えます。要件さえ満たせば非常に有用な在留資格であり、受入れ企業・留学生双方に新たな選択肢と可能性をもたらしています。
この記事を書いた人

- 行政書士Office ITO 代表
-
IT業界で10年目リストラに遭遇し、行政書士資格を取得。
2016年行政書士Office ITOを開設し、外国人ビザ申請に特化。
銀座を拠点に就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザなど実績10年。
趣味はおいしいパスタ料理(自称)と断捨離。家は小遣い制。
[ 所属団体 ] 東京行政書士会(会員番号 第11086号)
日本行政書士会連合会(登録番号 第16081519号)
[ 資格 ]
・Certified Administrative Procedures Specialist(行政書士)
・Certified Immigration Procedures Agent(入管申請取次)他
最新の投稿
 News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ
News & Updates2025-12-22年末年始休業期間のお知らせ Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは?
Column2025-11-18申請書の「交通違反等も含む」とは? News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)
News & Updates2025-10-18在留資格「経営・管理」― 要件厳格に。(2025年10月16日から)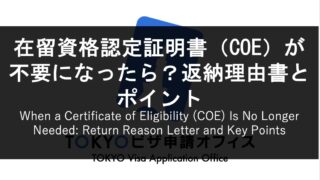 Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント
Column2025-05-29在留資格認定証明書(COE)が不要になったら?返納理由書とポイント